スパイクレシーブ(ディグ)の練習方法!上達するためのコツとは?
Sponsored Link
スパイクレシーブ(ディグ)の練習方法をお探しですか?今回はアンダーハンドによるスパイクレシーブ(ディグ)について説明していきます。
Sponsored Link
Contents
スパイクレシーブとサーブレシーブは全く違うもの!
相手の強打のスパイクをレシーブする時はアンダーハンドで受ける時が多くなりますよね。
中にはスパイクレシーブ(ディグ)とサーブレシーブ(レセプション)を同じレシーブと思い、同じような練習方法をしているチームがありますが、全くの間違いです。
スパイクレシーブ(ディグ)は相手チームのアタッカーがスパイクを打ってから、ボールがコートに落ちるまで0コンマ何秒と非常に短いため、スパイクレシーブ(ディグ)のフォームとポジョニング(位置取り)が大変重要です。
場合によってはファーストレシーブをオーバーハンドでレシーブすることもありますし、両手で間に合わない時だけ、ワンハンドでレシーブする時もあります。
では、練習方法を紹介していきます。
スパイクレシーブ(ディグ)の正しいフォーム

基本フォームはアンダーハンドパスやサーブレシーブと同様ですが、姿勢はサーブレシーブよりも低くして重心を足の親指に置いて前傾にします。
スパイクレシーブ(ディグ)をする場合は、
- 強打にそなえて低い構えで前傾姿勢をとり、さらに腰を沈める
- ボールがくる方向へ足を一歩踏み出し、体ごとボールにぶつけていく感じでレシーブする
- アゴを引き、レシーブの瞬間に両ヒジをしぼって球威を弱くする
【注意するポイント】
- 腕を振り、手だけでレシーブしてしまうとボールのコントロールができなくなる
- アゴが上がり、顔をそむけていると、ボールが手に正確に当たらなくなる
スパイクレシーブの練習方法
コートを使わない場合とコートを使って行う練習方法を紹介します。
2人の対人レシーブ
2人1組で行います。
片方がスパイクを打ち、それをもう片方がレシーブで返し、返ってきたボールをまたスパイクで打ち返します。スパイクが思った通りに打てない場合などは、直接投げても良いです。
これをスパイカーとレシーバー役として5分交代で行いましょう。
試合前などアップの時間がないときは、スパイカーとレシーバーを交互に行うといいですね。
◇交互に行う場合は、以下のようにすると効果的な練習が可能です。
- A-スパイクを打つ B-レシーブをする
- A-トスを上げる B-スパイクをする
- A-レシーブをする B-トスを上げる
- A-スパイクを打つ B-レシーブをする
以上を繰り返します。
【チェックポイント!】
- スパイカーはジャンプをしないで打つ
- スパイクを打ち終わったら構えて、すぐに次の動きに入る
- リズムよく繰り返すことが大切
スパイクと組み合わせて練習する
コートを使って、実際のスパイクをレシーブする練習です。この練習では、必ずどこに上げるか目標を明確にすることが大切です。基本はセッターの位置なので、そこへ上げられなければ、レシーブができたとは言えません。
ネットを使ってコートから実際にスパイクを打って、反対側のコートでレシーブを受けます。レシーブする側のコートには、レシーバーとセッターを置きます。
レシーブする人は後衛の左、中と右(レフト、センター、ライト)に3人を配置するのが理想ですが、メンバーの人数や目的に応じて変えても構いません。
レシーバーの後ろに、次にレシーブする人を待機させると効率的に練習ができます。5本上がったら交代などと決めておくと良いでしょう。なお、交代でコートに入るときは、かけ足で行います。
また、レシーブしたボールが、スパイカーの足元に行かないように、スパイカーの近くのネット際に必ず1人置くことを忘れないようにしましょう。
スパイクする方は、1本でも多くのスパイクを打たせたいので、コートに台を置いて台の上からジャンプせずに打つといいでしょう。
【チェックポイント】
- レシーブの順番を待っている間も、ボールのコースをよく見て研究すること
- セッターは動かずにキャッチできたボールに対しては、「ナイスレシーブ」などと声を掛けること
スパイクレシーブの上達方法

どこに打ってくるのか見極める
相手のスパイカーが打つ時の助走のコースや手元、およびセッターがトスを上げた位置などをすぐに把握して、すばやくボールが飛んでくるであろう位置に入ります。
ボールの下部分が見える位置へ動く
瞬時にコースを判断したら、ボールの下部分が見える位置でレシーブするという意識を持つと、ボールの落下地点にすばやく入れます。しっかりとディグの姿勢を低くとることで、すばやくボールのコースに反応できます。
相手がスパイクを打つときに、一歩前に出るような感じにすると、次の動作がスムーズにいくでしょう。
腕を振らず面にしっかり当てる
腕を振らずボールを当てるだけで、腕の面の角度がしっかりとしていれば簡単にボールが上がります。
腕を振ってしまうと腕の面がしっかりできずにボールを弾いてしまったり、ボールが勢いよくどこかに飛んでいくので、コントールが難しいレシーブになってしまいます。
ボールがきたら腕を振らないように注意してボールの勢いを吸収しましょう。
低い姿勢を維持できるようにストレッチする
前方に落ちるボールは、片手で上げにいってもうまくボールをコントロールできません。腕をしっかりと伸ばしてボールの落下地点に腕の面を置くように常に意識しましょう。
そのためには、腰を深く曲げた状態でボールの正面に入ることがとても大切です。体全体の柔軟性もストレッチをおこなって高めていきましょう。
動画で学ぶ!上達するスパイクレシーブ(ディグ)の練習方法とは?
この動画は社会人バレーボール、女子9人制のトップチームである富士通テン(現在はデンソーテン)の監督さんが指導している動画です。
ポイントは
- ボールから目を離さない
- 腕の角度は太ももと平行に
- 親指に力を入れる
- アンダーパスより足幅を広くヒザは深く
- 横のボールは肩をかぶせるようにとる
繰り返し練習してみましょう!
指導者が教えるスパイクレシーブ(ディグ)の悩み解決方法!
スパイクレシーブ(ディグ)の初心者がつまずく要因を挙げてみます。
- 怖くて腰が引ける
- 腕を振ってしまう
- 腕を組んだまま動いてしまう
- 足が全然動かない
- 片手でレシーブしてしまう
正直なところ、この悩みを解決するには練習を繰り返すしかありません。
一番の対処方法としては打つのがうまい人と対人レシーブをすることです。きちんとドライブをかけたボールを打ってもらうと良いレシーブの練習になります。
あとはスパイクレシーブがうまい人のプレーを見て、フォームとかどのタイミングで前に出てレシーブしているかを見て盗むことですね。
また、日本のトップ選手がプレーしているV・プレミアリーグの試合の放送をビデオで撮っていて、スパイクレシーブを参考にするのもよいと思います。
ぜひ頑張ってください!


↓この記事が役に立ちましたらランキングにご協力ください!↓
にほんブログ村
![]()
にほんブログ村
Sponsored Link
Sponsored Link
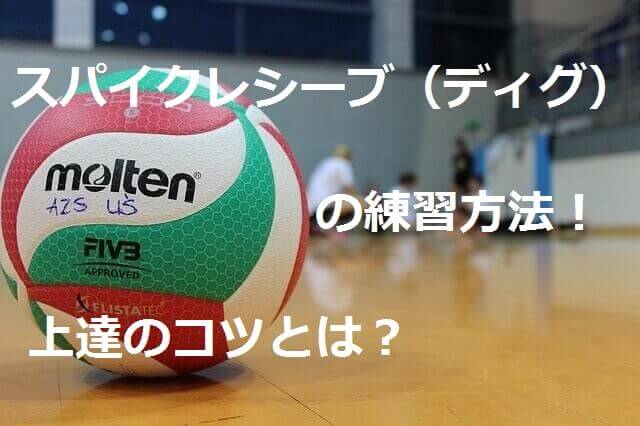
よって、ボールがくる方向へ一歩踏み出し、体ごとボールにぶつけていく感じでレシーブしましょう。怖がってしまうと、あごが上がり、顔をそむけてしまうため、ボールが手に正確に当たらなくなります。
また、腕は振らずに両ひじを絞って、球威を殺すようにします。手だけでレシーブするとコントロールできなくなります。
スパイクレシーブ(ディグ)はセッターに返すという意識よりも、とにかくボールを上に上げるという意識が重要です。あとはどんな強打を打たれても、レシーブは技術も必要ですが、絶対に上げてやると言う強い気持ちがとても大切です。